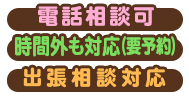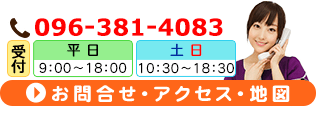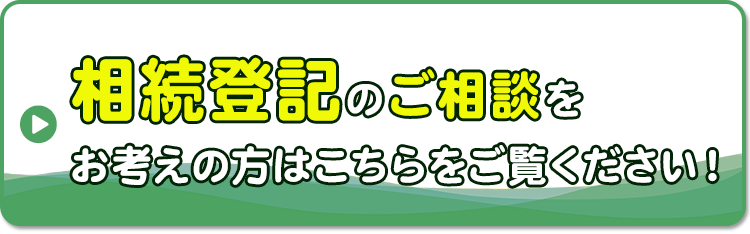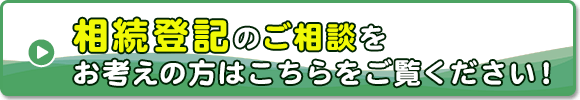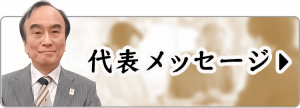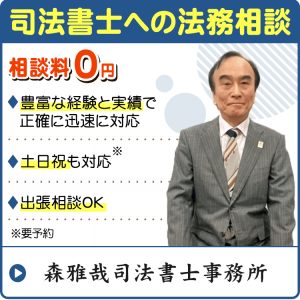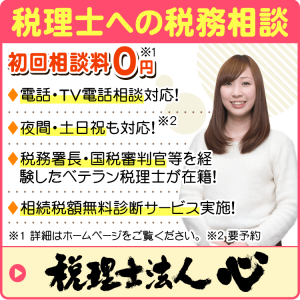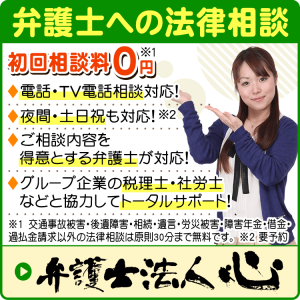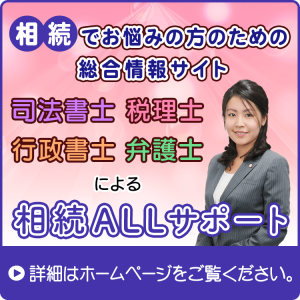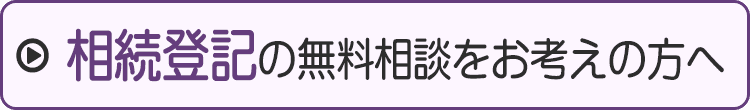農地を相続する場合の手続き
1 農地を相続できる相続人について
農地は、売買の際には農業委員会の許可が必要であるなどの制限が存在しますが、相続の場合には、他の不動産などと同様に、法定相続人であれば遺産分割協議によって取得することが可能です。
農地などの不動産を相続によって取得した場合には、相続登記を行う必要があります。
そして、相続によって農地を取得した場合には、権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に、農業委員会に届け出る必要があります。
なお、相続によって取得した農地であっても、第三者に譲渡する場合や、宅地に転用する場合には、原則として農業委員会の許可が必要となります。
相続自体には制限がなくても、その後は届出や、利用方法によっては許可が必要になる点に注意が必要です。
2 相続登記
農地に限りませんが、不動産を相続によって取得した場合、相続人に名義を変更するために相続登記を行う必要があります。
相続登記は、2024年4月から義務化されており、基本的には相続開始を知った日から3年以内に行わないと過料の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
また、相続登記は、後述する農業委員会への届出の際にも必要となります。
農業委員会への届出には期限がありますので、できる限り早めに相続登記をすることをおすすめします。
3 農業委員会への届出
農地を相続によって取得した場合には、農地法第3条の3に基づき、農業委員会への届出が必要となります。
届出先は、農地が存在する市町村の農業委員会です。
届出の期限は、権利を取得したことを知ってからおおむね10か月以内とされており、届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
届出の際には、登記事項証明書も必要となりますので、事前に相続登記を済ませておく必要があります。
この届出は、農地の利用状況の把握や適正な管理を目的としていることから、実際に相続人が農業を行うか否かに関わらず、行わなければなりません。