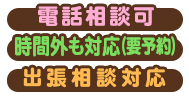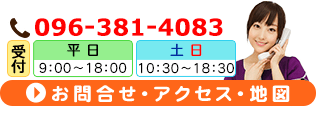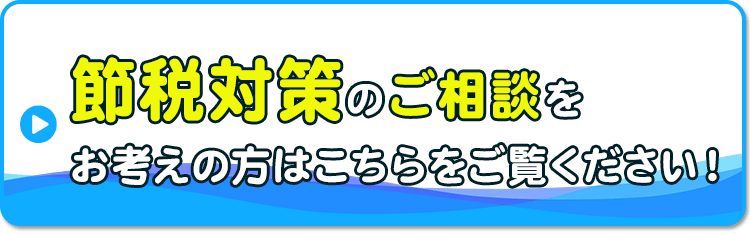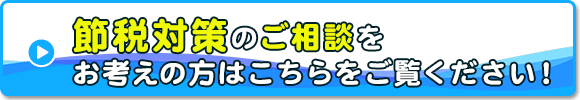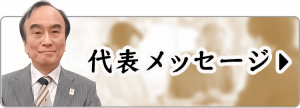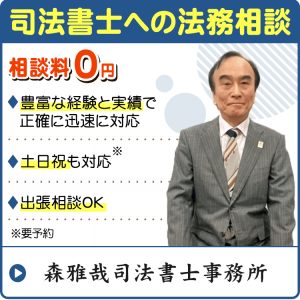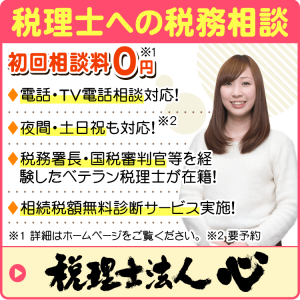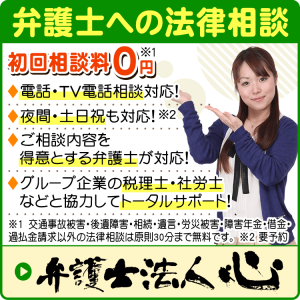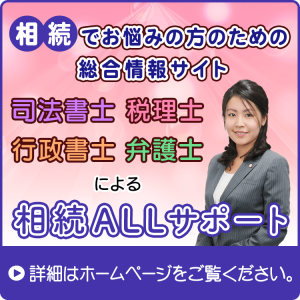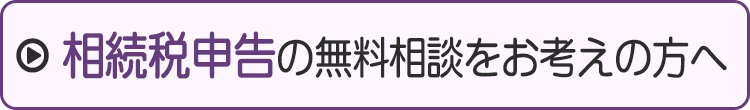相続時精算課税制度について
1 相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母又は祖父母より、成人(令和3年3月31日以前は20歳以上、令和3年4月1日以降は18歳以上)の子・孫に対して贈与がなされた場合に選択できる制度です。
2 相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度を選択していない場合、暦年贈与により、贈与税の課税がなされることとなります。
暦年贈与の場合は、毎年1月1日から12月31日までの贈与について、贈与を受けた翌年に申告・納税が必要となります。
暦年贈与では、毎年110万円までは非課税とされています。
他方で、相続時精算課税制度を使う場合、合計2500万円までは、贈与税がかからないというメリットがあります。
しかし、相続が発生した時点で、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産も相続財産に含めて計算しなければなりません。
このため、相続時精算課税制度を利用すると、税金の納付を相続時点まで先延ばしされることとなります。
また、一般的に相続税の方が贈与税よりも税率が低いので、その点では節税になり得ます。
3 相続時精算課税制度のデメリット
⑴ 一度選択したら暦年贈与には戻すことができない
現時点では、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年贈与に戻すことができません。
したがって、先に相続時精算課税制度を利用して2500万円を贈与し、その後、年間110万円ずつ贈与をしたとしても、非課税枠を使うことができないのです。
この場合、2500万円を超えてなされた贈与については、一律20%の贈与税が課されます。
暦年贈与により年間110万円ずつ贈与を続け、贈与税の負担なく相続財産を減らすという生前対策は、一般的によく使われる手法ですから、これを利用できなくなる点で、相続時精算課税制度を利用するタイミングは慎重に判断した方がよいです。
⑵ 毎年の申告が必要
相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行う場合、金額の大小にかかわらず贈与税の申告を必ず行わなければなりません。
相続時精算課税制度を選択したにもかかわらず、贈与税の申告が漏れてしまった場合には、合計の贈与額が2500万円に達していなかったとしても、一律20%の贈与税が課されることとなってしまいます。
暦年贈与の場合、毎年110万円以内の贈与であれば、申告を行わなくても非課税となりますので、そことの比較という点でいうと、申告の手間がかかることはデメリットといえるでしょう。
⑶ 小規模宅地の特例が使えない
土地を相続する場合、一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大50%~80%減額することができる小規模宅地の特例というものがあります。
土地は相続財産の中でも価値が大きくなりやすい財産の一つですので、その価値を大幅に減額できる小規模宅地の特例は、相続税申告の際に必ず知っておきたい特例といえます。
しかし、相続時精算課税制度を利用して土地の生前贈与が行われた場合、小規模宅地の特例は利用できません。
相続の際に小規模宅地の特例を利用できそうな土地については、相続時精算課税制度を利用しない方がかえって税負担軽減につながる場合もあり得ます。
4 さいごに
このように、相続時精算課税制度にはメリットもデメリットもあります。
相続時精算課税制度を利用すべきか迷ったら、税理士に相談してみてはいかがでしょうか。